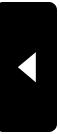2015年05月23日
かいのくち

( ノ゚Д゚)こんにちは!
おひさしぶりです。
長らく合間ができてしまいました(; ^ω^)
今日はちょっと地味…
いや、かなり…
いえ!しっとり落ち着きのあるゆかたの帯結びです

貝の口(かいのくち)
といいます!
なぜそう呼ぶのか…見たままで言うと、
貝が出水口入水口を殻から出している姿
に、似ているからでしょうかねぇ?(*・ω・)?
①帯を胴に二回まき(前回のお題の一文字とここまではいっしょですね)したら、胸にあずけてあった手先を体の中心におろして、
たれの方も体の中心から測って、手先と同じ長さまでを測ります。
この時めじるしとしてクリップなどで印つけしておくのもよいですね(´∀`)

この写真でたれの元がきれいに手の元と揃っているのは、わかりやすくあえてくりっぷなどで固定して留めてあるだけです(^^ゞ。

内側に折入れておきます。
②手はそのまま垂れ下げておいて (ง ˙ω˙)ว
①で決めた長さのままのたれを、その垂れ下げた手に巻きつけるように結びます。


③結んだたれのもとをととのえながら下げ、写真のようにおりあげます。
もうここまできたら結末がみえますよね(´Д⊂

④垂れ下げてあった手先を③で作ったあいた空間にとおします。

⑤形を整えてできあがり!

実際結んでみると帯の材質によっては手が抜けてきそうで不安

そんなときは、ゆかたでも帯締めをしてみるといいですよ。
カジュアルな帯締めも世にはありますし、
これについてはまた別の回で触れていきましょう。
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
2015年05月13日
たまにはみんなで。
毎月のブラッシュアップ

仲間や師匠と一緒に新しい帯型チャレンジしてみたり、
厳しくも(・`ω´・)」やさしく(´∀`)改善点を指摘したり、してくれたり(^^ゞ
初心にかえって学ぶのって大切ですね

昨日、薔薇をイメージ
 して作ってみた帯型。
して作ってみた帯型。
これを、今日は違う帯と違う着物のコーディネートで作ってみたら、これまた雰囲気も変わって。

帯のやわらかさや色、柄でずいぶんかわるなぁ(°ω° )
と再認識。
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
2015年05月12日
自主トレ~
雨ですね~
雨も降らないと困りますが、季節はずれの台風はこまりますね( ´・_・`)
何事もなく通り過ぎていってほしいものです
こんな日は、やや引きこもり気味
明るい帯型でも結んで少しでもきもちを明るく(´∀`)

華やかさのある帯型

向かって左羽にハートを潜ませてみました

雨も降らないと困りますが、季節はずれの台風はこまりますね( ´・_・`)
何事もなく通り過ぎていってほしいものです

こんな日は、やや引きこもり気味

明るい帯型でも結んで少しでもきもちを明るく(´∀`)

華やかさのある帯型


向かって左羽にハートを潜ませてみました

2015年05月11日
ゆかたの着付け4
こんにちは!
まだ五月だというのに台風発生∑(O_O;)
こんなに早い台風なんて聞いたことないです!
大雨対策しっかりと、皆様どうか無事にやり過ごせますように
ゆかたシーズンが本格的に始まったら台風さん には少し控えてもらいたいですね(๑•̀ㅁ•́ฅ✧
には少し控えてもらいたいですね(๑•̀ㅁ•́ฅ✧
さて、ゆかたのおび結びの「一文字」の仕上げです。

①手さきをリボンの真ん中をくるむように結ぶ、
くるんだ手先を…リボンの裏、手の根元、背中の間。この三点の間にできた空間に通して結び
(前回の一番最後にある写真を参照して下さい)
結んだあとの手先を、、、すこし強引ですが下方に引き下ろします。

②引き下ろした手先を胴に巻いた帯の内側に入れる。

はみ出した手先はおりあげてかくす(^_^;)
③リボンの形を整えて、右手でリボン部分(結び目あたり)をしっかり持ち、
左手で左脇の帯下端(ひと巻きめも、ふた巻きめも一緒に持つ)をしっかり持ち、
左手を体の中心、
右手を右脇に来るように、帯をすこしずつずらしていきます。

90度回したところ。
もう一度この手順を繰り返してリボンが背中の真ん中に来るようにします。
④手をおりあげて隠したところに、折りたたんだハンドタオル(薄手のものが扱いやすいかな)を入れる。
こうすることによって、帯の凹んだしわをとることができます。
でも、自分ではなかなか入れにくかったりしますのでだれかヘルプをたのみましょう(^^ゞ

⑤帯板を入れます。

このように縦方向から斜めに差し入れると入れやすいです。
完成!

いかがでしたでしょうか。
また、違う帯型も紹介していきますのでしばしお待ちください<(_ _)>
お問い合わせ先
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853

まだ五月だというのに台風発生∑(O_O;)
こんなに早い台風なんて聞いたことないです!
大雨対策しっかりと、皆様どうか無事にやり過ごせますように

ゆかたシーズンが本格的に始まったら台風さん
 には少し控えてもらいたいですね(๑•̀ㅁ•́ฅ✧
には少し控えてもらいたいですね(๑•̀ㅁ•́ฅ✧さて、ゆかたのおび結びの「一文字」の仕上げです。
①手さきをリボンの真ん中をくるむように結ぶ、
くるんだ手先を…リボンの裏、手の根元、背中の間。この三点の間にできた空間に通して結び
(前回の一番最後にある写真を参照して下さい)
結んだあとの手先を、、、すこし強引ですが下方に引き下ろします。
②引き下ろした手先を胴に巻いた帯の内側に入れる。
はみ出した手先はおりあげてかくす(^_^;)
③リボンの形を整えて、右手でリボン部分(結び目あたり)をしっかり持ち、
左手で左脇の帯下端(ひと巻きめも、ふた巻きめも一緒に持つ)をしっかり持ち、
左手を体の中心、
右手を右脇に来るように、帯をすこしずつずらしていきます。
90度回したところ。
もう一度この手順を繰り返してリボンが背中の真ん中に来るようにします。
④手をおりあげて隠したところに、折りたたんだハンドタオル(薄手のものが扱いやすいかな)を入れる。
こうすることによって、帯の凹んだしわをとることができます。
でも、自分ではなかなか入れにくかったりしますのでだれかヘルプをたのみましょう(^^ゞ
⑤帯板を入れます。
このように縦方向から斜めに差し入れると入れやすいです。
完成!
いかがでしたでしょうか。
また、違う帯型も紹介していきますのでしばしお待ちください<(_ _)>
お問い合わせ先
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
2015年05月11日
ゆかたの着付け3(一文字1)
更新遅れがちにて失礼しますm(_ _)m
今回から帯結びを進めていきましょう♪
まずは、ゆかたのおびでは、オーソドックスな「一文字」
リボン結び(⑅•͈૦•͈⑅)
①手先から、自分の胴体の幅(少し長くてもいいかも)の長さを半分に折り、クリップで留め
体の正面の位置にそのクリップで胴に巻いた伊達じめに留めます。

②胴に巻きやすいようにクリップで留めた位置を開いて、動かないようにまたクリップで留め直し、
手先は胸にあずけ
まずはひと巻きします。

留め直したところ
③ひと巻きしたら、左手はクリップ位置、右手は巻いた帯の下端をつかんで引いてよく締めます。
更にもうひと巻きして、同じように締めます。

ふた巻きしたところ
④ふた巻きしたら、右脇から体の中央の位置に向かって斜めにおりあげます。

おりあげられたことにより、体の中央位置では帯巾は半分になっています。
⑤胸にあずけてあった手でくるむように締めます。

手を上、たれを下


結んだタレ元は開いてほどけにくいようにしておきます。
⑥タレ先から、胴体の幅分の長さを測り、その長さをくるくるとまきたたんでおきます
この、胴体の幅、というのがリボンの大きさになるわけですね(´∀`)

⑦畳んだこのタレ。真ん中部分を山になるように折、更に端と端を折りあげてリボンのような形に整えます。

⑧手先でくるむようにリボンの真ん中を巻いて、ほどけないように結びます


それっぽくまとまってきました(∩´∀`)∩ワーイ
次回は、このリボンを整えて、背中にもっていきますよ。
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
今回から帯結びを進めていきましょう♪
まずは、ゆかたのおびでは、オーソドックスな「一文字」
リボン結び(⑅•͈૦•͈⑅)
①手先から、自分の胴体の幅(少し長くてもいいかも)の長さを半分に折り、クリップで留め
体の正面の位置にそのクリップで胴に巻いた伊達じめに留めます。

②胴に巻きやすいようにクリップで留めた位置を開いて、動かないようにまたクリップで留め直し、
手先は胸にあずけ
まずはひと巻きします。
留め直したところ
③ひと巻きしたら、左手はクリップ位置、右手は巻いた帯の下端をつかんで引いてよく締めます。
更にもうひと巻きして、同じように締めます。

ふた巻きしたところ
④ふた巻きしたら、右脇から体の中央の位置に向かって斜めにおりあげます。

おりあげられたことにより、体の中央位置では帯巾は半分になっています。
⑤胸にあずけてあった手でくるむように締めます。
手を上、たれを下
結んだタレ元は開いてほどけにくいようにしておきます。
⑥タレ先から、胴体の幅分の長さを測り、その長さをくるくるとまきたたんでおきます
この、胴体の幅、というのがリボンの大きさになるわけですね(´∀`)
⑦畳んだこのタレ。真ん中部分を山になるように折、更に端と端を折りあげてリボンのような形に整えます。
⑧手先でくるむようにリボンの真ん中を巻いて、ほどけないように結びます
それっぽくまとまってきました(∩´∀`)∩ワーイ
次回は、このリボンを整えて、背中にもっていきますよ。
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
2015年05月09日
ゆかたの着方2
こんにちは!(๑ゝω・ิ)ノ☆゚+.
今回は衿を合わせるところからです!!
①下前(自分の体の右側)の衿から揃えます。
左脇の身八つ口(脇の部分の空いているところのことです)から左手を入れて、下前の衿を掴んで合わせると合わせやすいです。
同様に上前の衿も合わせます。左右の衿が体の中心で均等に揃えられているか確認します。

のどのくぼみの少し下ぐらいで合わせられるといいかな。
「涼しげ」がモットーなゆかたなので衿元はつまり過ぎないように~。
左胸のアンダー辺りに、上紐(腰紐を衿合わせに使うときはこう呼んでます)の中心をあててしめます。
②背縫いが背中心からずれないように気をつけながら、上紐の下方から指を入れ左右に背中のシワをとります。

③おはしょりを整えます。
右手を上前のおはしょりの中に入れて、身体の左端の方ほど下前のおはしょりを上紐方面にズリ上げておくと
帯をしめたときには上前のおはしょりしか見えなくなるのでスッキリして見えます。
身体の右端で、上前のおはしょりと、後ろから来たおはしょりの高さを同じになるようにととのえます。
ずれてしまわないようにクリップで一旦とめておいてもいいでしょう。

④伊達じめをします。
おはしょりの下端から人差し指一本ほど上がった位置に伊達じめの下端がくるぐらいが目安です。

ひとまずこれで、ゆかたの着付けはできました(∩´∀`)∩ワーイ
次回からはいよいよ帯をしめます。
お問いあわせは
chiharu.makino@gmail.com
09081309853
0532-47-5525
今回は衿を合わせるところからです!!
①下前(自分の体の右側)の衿から揃えます。
左脇の身八つ口(脇の部分の空いているところのことです)から左手を入れて、下前の衿を掴んで合わせると合わせやすいです。
同様に上前の衿も合わせます。左右の衿が体の中心で均等に揃えられているか確認します。

のどのくぼみの少し下ぐらいで合わせられるといいかな。
「涼しげ」がモットーなゆかたなので衿元はつまり過ぎないように~。
左胸のアンダー辺りに、上紐(腰紐を衿合わせに使うときはこう呼んでます)の中心をあててしめます。
②背縫いが背中心からずれないように気をつけながら、上紐の下方から指を入れ左右に背中のシワをとります。

③おはしょりを整えます。
右手を上前のおはしょりの中に入れて、身体の左端の方ほど下前のおはしょりを上紐方面にズリ上げておくと
帯をしめたときには上前のおはしょりしか見えなくなるのでスッキリして見えます。
身体の右端で、上前のおはしょりと、後ろから来たおはしょりの高さを同じになるようにととのえます。
ずれてしまわないようにクリップで一旦とめておいてもいいでしょう。
④伊達じめをします。
おはしょりの下端から人差し指一本ほど上がった位置に伊達じめの下端がくるぐらいが目安です。

ひとまずこれで、ゆかたの着付けはできました(∩´∀`)∩ワーイ
次回からはいよいよ帯をしめます。
お問いあわせは
chiharu.makino@gmail.com
09081309853
0532-47-5525
2015年05月07日
ゆかたの着付け1

浴衣の着付け方、さらっとまいりましょう( ´ ▽ ` )ノ
①汗取りのため、肌襦袢、もしくはキャミソールなどを着た上に、ゆかたを羽織ります。

②背縫いが背中心に在ることを確認します。(以前の記事、着付け方にもあります)
軽く衣紋をぬきます。
とはいえ、抜きすぎると胸元までガバガバしてしまいますので注意。

こんくらい。

③衿先から手幅ひとつほどのところをガッツリ持ち、裾線(裾の長さ丈のことですね)を決めます。
涼しげに仕上げたいので、着物より短めに。くるぶしの位置ぐらいで。
④下前(右手で掴んでいる側)から体に沿わせて、左脇まで巻いたら、上前をかぶせるように合わせ、腰紐を締めます。

⑤前後のおはしょりを下ろして整えておきます。

と、駆け足できましたが(;・∀・)
詳しい解説はまた後ほど。
お問い合わせ先
chiharu.makino@gmail.com
2015年05月07日
立夏を過ぎ(๑º º๑)

こんにちは!
お久しぶりです(^-^)/
昨日、5月6日は「立夏」

暦の上では夏です!
…今日はくもりがちな空ですが(^^ゞ
夏が来ると、納涼祭りや花火大会など
ゆかたを着て出かけたい季節になってきました(ღˇᴗˇ)。o♡
そこで、また簡単ではありますが
浴衣の着付けを記して行こうと思います。
まずは、用意するもの

①浴衣
②ゆかた用帯(半幅帯など)
③腰紐2本
④伊達じめ
⑤帯板
⑥クリップ
⑦ハンドタオル
浴衣の下に着る下着は、いわゆる着物用の肌襦袢でも構いませんが、
下着の役目としては、
汗を取る。
ということですので、キャミソールなど洋服用の下着でも用いることができます。
ハンドタオルは何に使うかというと、後半で帯のシワを取るのに使います。
次回から軽くレクチャーしていきますね(´∀`)
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
0532-47-5525
09081309853
2015年03月10日
一重太鼓3
( ノ゚Д゚)こんにちは
今回は…今回こそ完成に近づけますよ(;・∀・)
①前にあずけてあった「て」を後ろに回します
「一重太鼓」なので、「て」をどこにとおすかというと、やっぱり一重なだけに
お太鼓の表から一枚目に通すわけです。


こんなふうに折り紙を折るように角をシッカリ折ると扱いやすいかな。
②帯締めを「て」の幅の真ん中を通るように通します。
「て」の真ん中=帯巾の真ん中(´∀`)

③体の中心で帯締めを交差して

②ひと締めします

③下側になっている方(この場合画面左)を反対方面(画面右)に流します。

④そしたら、もう一方の、下にだらんとたれていた方を、今右に流した帯締めの上によっこらせとあげて、

⑤そのまま、わ に通します。

⑥で、左右に引いて締めれば、帯締めできあがり~

おやおや、帯締めができたらほぼ完成ですよ。
あとは、仮紐を引き抜いて、帯がおちてこなかったら成功です!

これで、一重太鼓(いちじゅうだいこ)のできあがりです。
一重太鼓は、フォーマルなシーンにはNG ですが、
ですが、
お食事会や、観劇、初詣、などちょっとおしゃれして出かけたいときに最適です(*´∀`*)
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
0532-47-5525
今回は…今回こそ完成に近づけますよ(;・∀・)
①前にあずけてあった「て」を後ろに回します
「一重太鼓」なので、「て」をどこにとおすかというと、やっぱり一重なだけに
お太鼓の表から一枚目に通すわけです。
こんなふうに折り紙を折るように角をシッカリ折ると扱いやすいかな。
②帯締めを「て」の幅の真ん中を通るように通します。
「て」の真ん中=帯巾の真ん中(´∀`)
③体の中心で帯締めを交差して
②ひと締めします
③下側になっている方(この場合画面左)を反対方面(画面右)に流します。
④そしたら、もう一方の、下にだらんとたれていた方を、今右に流した帯締めの上によっこらせとあげて、
⑤そのまま、わ に通します。
⑥で、左右に引いて締めれば、帯締めできあがり~
おやおや、帯締めができたらほぼ完成ですよ。
あとは、仮紐を引き抜いて、帯がおちてこなかったら成功です!

これで、一重太鼓(いちじゅうだいこ)のできあがりです。
一重太鼓は、フォーマルなシーンにはNG
 ですが、
ですが、お食事会や、観劇、初詣、などちょっとおしゃれして出かけたいときに最適です(*´∀`*)
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
0532-47-5525
2015年03月04日
一重太鼓3
( ノ゚Д゚)こんにちは
途切れがちなこのシリーズ(;・∀・)
今日は帯枕を乗っけるところからです。

①はい、この写真のようにのっけます。
…って、これが慣れるまではホントに大変なのですが、コツはまたの機会に。
後ろに回した両手が帯で帯枕を包むような気持ちでもちながら、軽く上体を前に傾けつつ背負うと良いかな。

②ガーゼの帯揚げを体に密着させて緩まないように結び、帯と伊達じめの間に沈み込めておきます。

1、帯揚げは、絞りの場合は交差させて

2、かけるだけ。 結ばずに帯の下にしまいます。

絞り以外の帯揚げ、(綸子など、、)、は結んで仕舞います。

③帯枕の下は、あまった帯でごちゃっとしていますので、

④ちょっとわかりにくいですが、帯枕のしたで平たく、かつ帯の下端から飛び出さない程度の長さにあげたりして整えて
タレ先から指一本分位の長さの位置に仮紐をあてて、その、仮紐が帯の下端に沿うようにして固定します。

前側から見るとすっかり紐だらけです(´▽`*)アハハ
chiharu.makino@gmail.com
途切れがちなこのシリーズ(;・∀・)
今日は帯枕を乗っけるところからです。
①はい、この写真のようにのっけます。
…って、これが慣れるまではホントに大変なのですが、コツはまたの機会に。
後ろに回した両手が帯で帯枕を包むような気持ちでもちながら、軽く上体を前に傾けつつ背負うと良いかな。
②ガーゼの帯揚げを体に密着させて緩まないように結び、帯と伊達じめの間に沈み込めておきます。
1、帯揚げは、絞りの場合は交差させて
2、かけるだけ。 結ばずに帯の下にしまいます。
絞り以外の帯揚げ、(綸子など、、)、は結んで仕舞います。
③帯枕の下は、あまった帯でごちゃっとしていますので、
④ちょっとわかりにくいですが、帯枕のしたで平たく、かつ帯の下端から飛び出さない程度の長さにあげたりして整えて
タレ先から指一本分位の長さの位置に仮紐をあてて、その、仮紐が帯の下端に沿うようにして固定します。
前側から見るとすっかり紐だらけです(´▽`*)アハハ
chiharu.makino@gmail.com