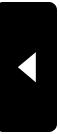2015年05月07日
立夏を過ぎ(๑º º๑)

こんにちは!
お久しぶりです(^-^)/
昨日、5月6日は「立夏」

暦の上では夏です!
…今日はくもりがちな空ですが(^^ゞ
夏が来ると、納涼祭りや花火大会など
ゆかたを着て出かけたい季節になってきました(ღˇᴗˇ)。o♡
そこで、また簡単ではありますが
浴衣の着付けを記して行こうと思います。
まずは、用意するもの

①浴衣
②ゆかた用帯(半幅帯など)
③腰紐2本
④伊達じめ
⑤帯板
⑥クリップ
⑦ハンドタオル
浴衣の下に着る下着は、いわゆる着物用の肌襦袢でも構いませんが、
下着の役目としては、
汗を取る。
ということですので、キャミソールなど洋服用の下着でも用いることができます。
ハンドタオルは何に使うかというと、後半で帯のシワを取るのに使います。
次回から軽くレクチャーしていきますね(´∀`)
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
0532-47-5525
09081309853
2015年03月10日
一重太鼓3
( ノ゚Д゚)こんにちは
今回は…今回こそ完成に近づけますよ(;・∀・)
①前にあずけてあった「て」を後ろに回します
「一重太鼓」なので、「て」をどこにとおすかというと、やっぱり一重なだけに
お太鼓の表から一枚目に通すわけです。


こんなふうに折り紙を折るように角をシッカリ折ると扱いやすいかな。
②帯締めを「て」の幅の真ん中を通るように通します。
「て」の真ん中=帯巾の真ん中(´∀`)

③体の中心で帯締めを交差して

②ひと締めします

③下側になっている方(この場合画面左)を反対方面(画面右)に流します。

④そしたら、もう一方の、下にだらんとたれていた方を、今右に流した帯締めの上によっこらせとあげて、

⑤そのまま、わ に通します。

⑥で、左右に引いて締めれば、帯締めできあがり~

おやおや、帯締めができたらほぼ完成ですよ。
あとは、仮紐を引き抜いて、帯がおちてこなかったら成功です!

これで、一重太鼓(いちじゅうだいこ)のできあがりです。
一重太鼓は、フォーマルなシーンにはNG ですが、
ですが、
お食事会や、観劇、初詣、などちょっとおしゃれして出かけたいときに最適です(*´∀`*)
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
0532-47-5525
今回は…今回こそ完成に近づけますよ(;・∀・)
①前にあずけてあった「て」を後ろに回します
「一重太鼓」なので、「て」をどこにとおすかというと、やっぱり一重なだけに
お太鼓の表から一枚目に通すわけです。
こんなふうに折り紙を折るように角をシッカリ折ると扱いやすいかな。
②帯締めを「て」の幅の真ん中を通るように通します。
「て」の真ん中=帯巾の真ん中(´∀`)
③体の中心で帯締めを交差して
②ひと締めします
③下側になっている方(この場合画面左)を反対方面(画面右)に流します。
④そしたら、もう一方の、下にだらんとたれていた方を、今右に流した帯締めの上によっこらせとあげて、
⑤そのまま、わ に通します。
⑥で、左右に引いて締めれば、帯締めできあがり~
おやおや、帯締めができたらほぼ完成ですよ。
あとは、仮紐を引き抜いて、帯がおちてこなかったら成功です!

これで、一重太鼓(いちじゅうだいこ)のできあがりです。
一重太鼓は、フォーマルなシーンにはNG
 ですが、
ですが、お食事会や、観劇、初詣、などちょっとおしゃれして出かけたいときに最適です(*´∀`*)
お問い合わせは
chiharu.makino@gmail.com
0532-47-5525
2015年03月04日
一重太鼓3
( ノ゚Д゚)こんにちは
途切れがちなこのシリーズ(;・∀・)
今日は帯枕を乗っけるところからです。

①はい、この写真のようにのっけます。
…って、これが慣れるまではホントに大変なのですが、コツはまたの機会に。
後ろに回した両手が帯で帯枕を包むような気持ちでもちながら、軽く上体を前に傾けつつ背負うと良いかな。

②ガーゼの帯揚げを体に密着させて緩まないように結び、帯と伊達じめの間に沈み込めておきます。

1、帯揚げは、絞りの場合は交差させて

2、かけるだけ。 結ばずに帯の下にしまいます。

絞り以外の帯揚げ、(綸子など、、)、は結んで仕舞います。

③帯枕の下は、あまった帯でごちゃっとしていますので、

④ちょっとわかりにくいですが、帯枕のしたで平たく、かつ帯の下端から飛び出さない程度の長さにあげたりして整えて
タレ先から指一本分位の長さの位置に仮紐をあてて、その、仮紐が帯の下端に沿うようにして固定します。

前側から見るとすっかり紐だらけです(´▽`*)アハハ
chiharu.makino@gmail.com
途切れがちなこのシリーズ(;・∀・)
今日は帯枕を乗っけるところからです。
①はい、この写真のようにのっけます。
…って、これが慣れるまではホントに大変なのですが、コツはまたの機会に。
後ろに回した両手が帯で帯枕を包むような気持ちでもちながら、軽く上体を前に傾けつつ背負うと良いかな。
②ガーゼの帯揚げを体に密着させて緩まないように結び、帯と伊達じめの間に沈み込めておきます。
1、帯揚げは、絞りの場合は交差させて
2、かけるだけ。 結ばずに帯の下にしまいます。
絞り以外の帯揚げ、(綸子など、、)、は結んで仕舞います。
③帯枕の下は、あまった帯でごちゃっとしていますので、
④ちょっとわかりにくいですが、帯枕のしたで平たく、かつ帯の下端から飛び出さない程度の長さにあげたりして整えて
タレ先から指一本分位の長さの位置に仮紐をあてて、その、仮紐が帯の下端に沿うようにして固定します。
前側から見るとすっかり紐だらけです(´▽`*)アハハ
chiharu.makino@gmail.com
2015年02月28日
一重太鼓2
お久しぶりです!
一週間ぶりの更新になります(;・∀・)アセリ
パソの不調を訴えてしばらく停止してましたが、こうしてなんとか作業できています。
さて、これからの動作としては、腕を後ろにまわす動作が多くなります
最初はなかなかに厳しい体勢かもしれませんが、回数こなすうちに肩甲骨あたりもよく動くようになって
楽にお太鼓作れるようになるので、頑張ってみましょう!
①タレ先から手幅にして四つ、か、4つ半くらいの位置をはかり、
その裏側に 飾り帯揚げをかけた、枕をはさみます。

補足 ①枕、あるいはお太鼓枕とよばれています、ウレタンなどでできた枕状の型です。
これに、ガーゼをかけておきます。

こんな感じ。
ガーゼのながさは胴にまいて結べる程度です。
なぜ、ガーゼなのかというと、引っ張られる力に強く、体へのあたり(とくに脇部分)がほかの素材よりもやさしいからです。
②この上に飾り帯揚げをかけるのですが、絞りの帯揚げの場合は表と裏を間違えないように注意しましょう。

コレ表

裏 おもてとは違って絞りのぽつぽつが凹んでます。

で、真ん中で輪ゴムなどで固定しておきます。(写真は枕の裏側を見たところです。)
一週間ぶりの更新になります(;・∀・)アセリ
パソの不調を訴えてしばらく停止してましたが、こうしてなんとか作業できています。
さて、これからの動作としては、腕を後ろにまわす動作が多くなります

最初はなかなかに厳しい体勢かもしれませんが、回数こなすうちに肩甲骨あたりもよく動くようになって
楽にお太鼓作れるようになるので、頑張ってみましょう!
①タレ先から手幅にして四つ、か、4つ半くらいの位置をはかり、
その裏側に 飾り帯揚げをかけた、枕をはさみます。
補足 ①枕、あるいはお太鼓枕とよばれています、ウレタンなどでできた枕状の型です。
これに、ガーゼをかけておきます。
こんな感じ。
ガーゼのながさは胴にまいて結べる程度です。
なぜ、ガーゼなのかというと、引っ張られる力に強く、体へのあたり(とくに脇部分)がほかの素材よりもやさしいからです。
②この上に飾り帯揚げをかけるのですが、絞りの帯揚げの場合は表と裏を間違えないように注意しましょう。
コレ表
裏 おもてとは違って絞りのぽつぽつが凹んでます。
で、真ん中で輪ゴムなどで固定しておきます。(写真は枕の裏側を見たところです。)
2015年02月22日
一重太鼓1
( ノ゚Д゚)こんにちは!
更新遅くて失礼しました!m(_ _)m
今回は、名古屋帯にて一重太鼓を締めていきましょう。
聞きなれない語句が出てくるかと思いますので、若干の説明を
てさき : 手先というのは、帯の端っこのことです。帯は胴に巻くところは半分に折って使うので、その半分幅側です。
たれさき : たれ先というのは、手先の反対側。背中に背負う側の端っこですね。
仮紐 : メインで使う紐とは別に、仮止めのためだけにつかい、あとで外したりする紐のことです。
①名古屋帯の「てさき」を持ち、右胸にあずけます。

これくらいの長さを右胸に。
この時、帯の手先は半分におっておるのですが、折った山部分を下にして巻いていきます。
この折った山部分を「わ」と呼びます。
②「わ」を下にして胴にひと巻きします。


ひと巻きしたら「て」を胸から外して左脇まで外し、↑のように左右均等に引いて締めます。
③ふた巻き目を巻いていきます。この時ひと巻き目との間に帯板をはさみます。
(胴に巻いていくふた巻き目の帯の半分に折ってある間。でもいいです)

ふた巻きしたら、ひと巻き目と同様に、帯の下端を持って左右に引いて締めます。
④左脇にあった「て」を背中の真ん中、背中心まで抜きます。
気持ち上に引き上げる感じで背中まで持っていくとよいかな?と思います。

⑤残るは「たれ」側ですが、背中の真ん中で先ほど持ってきた「て先」と交差させて右肩にあずけます。

※背中の真ん中で斜め上におりあげる訳ですから慣れるまでは大変かと思います。
巻いた帯がゆるまないかと心配になると思いますが、 ④の写真のように右手でタレの下端部分を右方向へ意識して引いて持っていればだいじょうぶです。
⑥「て」と「たれ」を交差したところに仮紐をかけて、あとで解くことができるように帯の上で結んでおきます。

⑦「て」は前に一旦あずけて、クリップなどでとめておきます。
このとき、「わ」が下になるようにします。

⑧「て」と「たれ」が交差している背中心部分、「たれもと」は帯の幅に開いておきます。

そしていよいよお太鼓部分なのですが、パソコンが不安定なようす
とりあえずは今回はここまで!
なるべく早い更新を
お問い合わせ
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
更新遅くて失礼しました!m(_ _)m
今回は、名古屋帯にて一重太鼓を締めていきましょう。
聞きなれない語句が出てくるかと思いますので、若干の説明を

てさき : 手先というのは、帯の端っこのことです。帯は胴に巻くところは半分に折って使うので、その半分幅側です。
たれさき : たれ先というのは、手先の反対側。背中に背負う側の端っこですね。
仮紐 : メインで使う紐とは別に、仮止めのためだけにつかい、あとで外したりする紐のことです。
①名古屋帯の「てさき」を持ち、右胸にあずけます。
これくらいの長さを右胸に。
この時、帯の手先は半分におっておるのですが、折った山部分を下にして巻いていきます。
この折った山部分を「わ」と呼びます。
②「わ」を下にして胴にひと巻きします。
ひと巻きしたら「て」を胸から外して左脇まで外し、↑のように左右均等に引いて締めます。
③ふた巻き目を巻いていきます。この時ひと巻き目との間に帯板をはさみます。
(胴に巻いていくふた巻き目の帯の半分に折ってある間。でもいいです)
ふた巻きしたら、ひと巻き目と同様に、帯の下端を持って左右に引いて締めます。
④左脇にあった「て」を背中の真ん中、背中心まで抜きます。
気持ち上に引き上げる感じで背中まで持っていくとよいかな?と思います。
⑤残るは「たれ」側ですが、背中の真ん中で先ほど持ってきた「て先」と交差させて右肩にあずけます。
※背中の真ん中で斜め上におりあげる訳ですから慣れるまでは大変かと思います。
巻いた帯がゆるまないかと心配になると思いますが、 ④の写真のように右手でタレの下端部分を右方向へ意識して引いて持っていればだいじょうぶです。
⑥「て」と「たれ」を交差したところに仮紐をかけて、あとで解くことができるように帯の上で結んでおきます。
⑦「て」は前に一旦あずけて、クリップなどでとめておきます。
このとき、「わ」が下になるようにします。
⑧「て」と「たれ」が交差している背中心部分、「たれもと」は帯の幅に開いておきます。
そしていよいよお太鼓部分なのですが、パソコンが不安定なようす

とりあえずは今回はここまで!
なるべく早い更新を

お問い合わせ
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
2015年02月17日
着付け方7
( ノ゚Д゚)こんにちは
今日の7回目
おはしょりを整えて、伊達じめを締める。
です。
①右手をおはしょりの中に通して手をパー
 にしながら自分から見て左から右へとおはしょりのシワをなくすようにして整えます。
にしながら自分から見て左から右へとおはしょりのシワをなくすようにして整えます。こんな感じ↑
②体の右脇で、前後のおはしょりの高さが揃うように整えます。
この時揃ったおはしょりを伊達じめヲ締めるまで固定しておく意味でクリップで押さえておくと安心でしょう。
揃ってるね。
③おはしょりを下から軽くなで上げるような手つきで伊達締めをあて、締めて
とりあえずは「着物の着付け」まで完成です\(^o^)/
次回からは帯結びです。
名古屋帯による一重太鼓です。
chiharu.makino@gmail.com
2015年02月16日
着付け方6
こんばんは( ノ゚Д゚)
なかなか進まない、このハウツー(^_^;)
読んでくださってる方ありがとうございます。
さて、衿合わせを進めていきましょう。
①下前(自分にとって右のむねから)の襟から揃えます。
左手を、左の身八つ口からてをいれて、下前をつかみ、衿を、衿の幅を整えます。
どれぐらいの幅で衿を、長襦袢の衿を出せばいいの?
一応ここでは、指先端から一節半ぐらいので加減がよくいです。
それが、上の写真です。
②上前の衿も同じように整えます。
写真のように、右手で合わせた衿元を押さえながら空いた手で上紐をとります。
③上紐の中心を左胸の下にとり、締めます。
④長襦袢でしたのと同じように、背中のシワをとります。
今日はここまでで失礼します

次回はおはしょりなど…
2015年02月15日
着付け方5
( ノ゚Д゚)こんにちは
そして。
大変失礼いたしました。ごめんなさい(._.)
昨日の夜、スマホからアップした「着付け方第四回目」
が、写真のサイズといい、「衿止め」を「衿合わせ」と間違えたり

情けない記事でして(;_;)
訂正しておきましたので、またよろしかったら、飽き飽きしてなかったら
 ご覧ください。
ご覧ください。気をとりなおしまして

着物の丈。裾の丈ですね。
これを決めて、そして腰紐で締めて裾の長さを固定します。
①衿先から手幅ぐらいの位置をガッツリ持ち、体の真ん中で前方にピン!と引っ張り、背骨の上に背縫いがあるか確認。
背中心を確認するということですね。
写真では人に着付けてあげる感じですが、
自分で着る時も同様です。
②裾線を決めて…
カジュアルな木綿やウールの着物はかかとスレスレぐらい、
フォーマルな着物、訪問着などは床に若干つくぐらい、、、
と、この辺はまた別の機会で詳しく(^_^;)
おっとと、裾線を決めたら下前(自分で見て右手で持っているほうですね。この写真では向かって左からですが…)を巻き込み
そしたら上前(自分で見て左手でもっている方ね)を被せて。
③腰紐を締めて着物の裾、着たときの丈を固定します。
この写真のように、腰紐の長さの中心を着物の合わせとは反対側にしたほうが着やすい。かなぁ と思います。
「腰紐の長さの中心」というのは要するに、そこが結び目となるから、
もし、着物の合わせと同じ場所に結び目があるとごろついて着心地がイマイチかなぁ~(^_^;)と個人的感想ですが。
ちなみに、腰紐を締める位置は、腰骨の上がいいです。
おなかでいうと、おへその少し下あたりを紐が通る感じ

胃袋を圧迫せずにしっかりと結べます。
④腰紐を締めたら、前後の「おはしょり」を下ろして、腰紐を締めたことによってダブついた布をピシ!と整えます。
次回は、次回こそは
衿合わせ
です(´▽`)
お問い合わせ先
chiharu.makino@gmail.com
090-8130-9853
2015年02月14日
着付け方4
さてさて。
遅ればせながら着物を羽織るところから説明していきましょう。
①お袖を通して、長襦袢と着物の袖の振りを揃えます。
②長襦袢でもしたように、共衿を左右揃えて顔の真ん中に来てるかなー。と、確認したら、
片手に持ち替え、空いた方の手で着物の背縫いが背骨の上。「背中心」に来ているか確認します!
③そしたら、
この写真のように着物の衿の後ろ真ん中が、長襦袢の衿よりも5ミリくらい高くなるように。
そして、衿片山の延長上。わかりやすく言うと耳のした辺り。で、長襦袢と着物の衿の高さが同じになるようにクリップ(写真では赤いクリップがついてますね)で固定しておきます。
と、少し進度が遅いのですが今日はここまででf^_^;)
2015年02月09日
着付け方3
( ノ゚Д゚)こんにちは!
前回に引き続き「長襦袢」です。
今回は「衿合わせ」です。
前回、衣紋の抜き加減と背中心の確認の仕方を書きました。
その衣紋を前に引っ張らないように、肩から前を意識して襟を合わせます。
衿合わせも、年代やシーンにより変わります。
基本は、のどのくぼみ下で左右の衿が交差する。ぐらいですが、
若い方は深く合わせる
年齢を重ねるほど浅い合わせ
①下前の衿(自分から見て右)から合わせます。
左手を左の身八つ口(脇の空いている部分)から通して下前の衿を迎えに行きます。
衿のふちがのどのくぼみの下にくるような感じで。
②上前の衿(自分から見て左)を合わせます。
右手で衿を持ち、襟のふちがのどのくぼみ下を通る感じで合わせます。
ん?両手がふさがってしまいましたね(´・∀・`) どうしましょぅ。
いえいえ左手を身八つ口から出して。右手で上前の衿ともども抑えているので左手はフリーになります。
その手で衿の合わさっている部分。胸の谷間あたり。を押さえ、
空いた右手で紐(ひも)をとり、
バスト下で結びます。
そしたら、背中のシワをとります

いましめた紐の下から指を通し、シワを左右に寄せます。
③伊達じめをしめます
ちょっと駆け足ぎみで説明しましたが、ここまでが長襦袢の着付けです。
さて、次から着物です。
ちょっと個人的事情により、週末あたりに更新します。 続きを読む