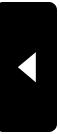2015年02月08日
着付け方2
( ノ゚Д゚)こんにちは!
前回に続いて。今回は「長襦袢」です。
上の写真は、長襦袢を着るときから気をつけたい「衣紋」の抜き加減を表しています。
フォーマルな場面(成人式、結婚式など各種式典)
と、
カジュアルな場面(観劇、お食事、など)
では、衣紋の抜き加減が違いますが、
今回は初歩的なところ、カジュアルな場面として説明します。
さて、長襦袢をはおるところから
①長襦袢に袖をとおしたら、左右の共衿をツマミ、体の前中心にあるか確認します。
共衿?そう、それは写真中心あたりの衿の上にもう一枚重ねてあるところ、
衿が二重になっているところです。
ここで、左右の衿先、及び共襟が体の中心にあるということは、、、
自然と、背中の真ん中の縫い目、これを「背縫い」と言いますが、
背縫いが背骨の上。つまり、「背中心」である。
といえます。
とはいえ、確認。確認。
②共襟を持っている手を片手に持ち替えて、
もう片方の手で、背縫いが背中心にあることを確認します。
③そしたら、背縫いをつまんだ手を下方向に少しずつひき
衣紋を抜きます。
カジュアルな着こなしですので、衣紋の抜き加減は
首からゲンコツ一個入るぐらいの空き具合です。
ここまでで、結構
めんどくさ~
と、思われるでしょう(^_^;)
でも、この、一連の動作は、このあとの「着物の着付け」でも大いに役立つので、
着物を着る時の無意識動作。ルーティンワーク。ぐらいになれるといいですね。
というか、数回、自分で着てみると自然に身につくと思うので多分大丈夫(^_^;
背縫いがきれいに背中心にある。
という状態は、きれいな着こなしの条件の一つでもあります(^-^)/
次回は「衿合わせ」
についてです。
お問い合わせ先
2015年02月07日
国家検定のてんまつ最終話
国家検定一級着付け技能士

「合格率4割ほど。一発合格は難しいよ。」
と聞いており、ビビって。しかし、がむしゃらにお稽古して挑んだ一級。
先のブログでもあげましたが、試験当日も試験官から注意されるわ
モデルさんは具合が悪くなるわで。
「今年はもうだめだろう」
と思っていた矢先に。
やったー!
合格ぅぅ⊂´⌒⊃゚Д゚)⊃ぅぅ!!
あきらめないで最後までやり遂げるといいことありますね!!
これからも頑張りますよ!
精進精進!!
2015年02月07日
着付け方1
( ノ゚Д゚)こんにちは
この写真の訪問着は去年、国家検定二級技能士の試験で使ったものです(´∀`)
そして、今年チャレンジした国家検定一級も奇跡的に一発合格できましたーv(=^0^=)v
という前振りから、、、
着物の着方を簡単にレクチャーできたらなとおもいます。
興味のある方はサラッと読んでみてくださいm(_)m
①足袋を履く
②肌襦袢を着る
誰でもわかるわー!
と言う突っ込みもありましょうが(^_^;)
この時気をつけたいのが「えもん」です。
このように首の後ろはおおきく開けておきましょう。
後に後ろ姿のキレイさの鍵です。
ハイ。肌襦袢が着られましたので
次は長襦袢です。
続きを読む2015年01月28日
みのほど~ヽ(´Д`;)ノ
着物と接してかれこれ二十年。
まだまだ着装道の修行は続く私です(´ε`;)
そんな私がまだ自分で着物が着られなかった頃の黒歴史

かなり前に黒歴史のカテゴリーでかるーく触れましたが、
家族が、着物を買いまくってた話。
その中でも一番高価な買い物が、7桁台価格の大島紬でしょう。
当時、私は着物は着られませんでしたが、もう値段見る前から
これは初心者が手を出すのは難しい着物だ~ (´д゚`ll)
と思いましたよ。
高価な紬は…さらりと、イキに洒落て着るものだと思うからです。
普段の生活の中で、あるいはちょっと洒落てレストランにお食事、などのシーンで着るもの。
と、いうことはズブの着物ビギナー。しかも自分で着られない人がどうやって、いつ、着るの(つд⊂)
ダメダメ。紬はフォーマルな場所で着ては。
この頃を思い返すとホントに着物には悪かったなぁ。と。
職人さんが一生懸命作ったものなのに。
着物には罪はないですからねぇ

「見栄」とか「勧められたら断れなくて」
とかいう理由で着物は買うものではないですな

着物が難しい。
と思うとき。
それは、「格」です。
結婚式のおよばれなどで着ることもある「着物」でも、
どんなに高価でも紬では、失礼にあたります。
例えて言うなら、
高価なブランドで、素材や品質が最高なカジュアルセーターとかTシャツで、結婚式や式典などのセレモニーに参加する(まぁそんな人はまずいないですけど例えなのでお許しを)なら、
安くても、化繊でも、レンタル落ち品でもフォーマルスーツやドレスの方がよい。
ということです。
極端な例を挙げてしまいましたが、
しかも着物着付師のくせに、
フォーマルスーツ、フォーマルドレスさいこー!
みたいな発言でちぐはぐですが(^_^;)
おや!後半は黒歴史から離れてしまいましたね

2015年01月28日
着るときにいるもの
( ノ゚Д゚)こんにちは!
新しい年を迎えてから、もう28日も経ってしまいましたね(^_^;)
私も正月から着物着てお出掛けしたり、
成人式の振袖着付けをさせていただいたり
一年で最も着物に触れる月でした
寒さも一番厳しい頃ですが
着物。
着てみると結構暖かいですよ
画面右上から下に向かって
帯 (これは名古屋帯)
帯板
帯締め(ここに写っているのは平組み)
ガーゼの帯揚げを被せた 帯枕(このかぶってるガーゼで胴に固定します。)と、飾り帯揚げ(芥子色のやつです
着物(これがなくちゃね(;^ω^))
腰紐 三本(補正用などに,,,予備としてもう1、2本あると良い)
伊達じめ2本
足袋
長襦袢(和装をスーツ姿に例えるとブラウスにあたるかなぁ)
肌襦袢(汗取りに、、、ザ肌着!)
習い始めはこれらですらチンプンカンプンでした。
腰紐三本、って?
ってな具合です(;´д`)
ほかにも、体型の補正にタオルやコットンを使ったり、
おはしょりをきれいに整えるウエストベルト
襟元の乱れを防止するコーリンベルト
和装ブラ、和装ストッキング
などなど
でも、とりあえず、これだけあれば。。。
というものをならべてみました
次回はこれらをボディーに着付けていってみましょうか。
2015年01月14日
朝の空の翼

おはようございます!今年1枚目のブログになります!
朝焼けが、まるで翼のように広がる雲に映えて迫力ありました!(◎_◎
朝焼け雲が羊雲に繋がって、キィン!と身の引き締まるような朝。
飛翔の翼と羊年とかけまして(^_^;)
今年もよろしくお願いしますm(_ _)m
って遅ればせながらよろしくお願いします‼︎( ´ ▽ ` )ノ
2014年12月17日
強風ですね✽彡
風の強い日です。
朝の寒さとあいまってちぢこまりそうになりますが

冬ならではの低い雲に朝日が射して

眩い光のすじ!
何か降臨してきそう!!

寒さと光で凛とした気持ちになれます(^-^)
2014年12月15日
2014年12月13日
着物たたみ方
今日は着物のたたみ方についてさらっと記していきたいと思いますヽ(*´∀`)ノ
まずは、一日着終わって 「お疲れ様(o´Д`)=з」 なお着物を
衣紋掛けなどに吊るし干して、湿気を飛ばし、ホコリをはらい、
直射日光のあたらない室内でいちにちゆっくり休めまして、、、
さて、たたんでいきましょう。
①
こんな感じで大体広げます。
着物の左前見頃(写真画面ですと、右側の白い裏地が見えるように翻っている)を おくみつけ線で、写真のように裏地が見える感じで折り返しておきます。
②
①で折り返した左前見頃の 衿先 と 裾 に注目して、
着物の右前身頃の 衿先 を左前見頃の衿先に、
着物の右前身頃の 裾 を左前見頃の裾に
合わせていきます。
そうするとこんな感じ↑
えりも衿先から同じように左右で合わせておきます。
③
そしたら、着物の右脇の 脇線 を左脇の 脇線 に合わせます。
そうすると、
この写真のように、背中の真ん中の線(背縫い)で真半分になって細~くなります。
④
お袖を見頃に沿わせて
あとはしまうサイズに合わせて、裾から三つ折、四つ折などして仕舞います。

いかがでしょう、
まだ、説明不足なところもあるかな。
また追って詳細や名称など説明していこうと思います

♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦♦♫♦・*:..。♦♫♦*゚¨゚゚・*:..。♦
chiharu.makino@gmail.com
〒441-8113 西幸町字幸33-10
☎0532(47)5525
牧野 千晴
2014年12月11日
たたみ方とか…
今日のおびがた~
こんなん結んでみました~

さて!
12月もど真ん中になってまいりました

クリスマス
 ムードも盛り上がってきている頃でしょうか。
ムードも盛り上がってきている頃でしょうか。受験生をかかえたる我が家ではなかなか
「
 パーリィ!!!
パーリィ!!! 」
」とはしゃいではいられませんが(´ε`;)
お正月ぐらいは
 餅でも食べて
餅でも食べて自らが鏡餅になるくらいの勢いで
 正月を味わうとします。
正月を味わうとします。お正月といえば
「着物でも…」
と、着てみようかなと思われる方、また、成人式の前撮りなどでお召になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、着物を広げて
さて、しまう時にたたみ方はご存知でしょうか??え、バカにするなですって(-_-;)はい。失礼しました

…いや、でも、意外と、
着物を持ってるけど、たたみ方知らない。
という方々に遭遇してきたので、ここでひとつ、、、
ブログのネタにでも。。。
もとい、「今更聞けない
 」
」という方に向けて次回より、すこしばかり書いていこうと思います。
続きを読む